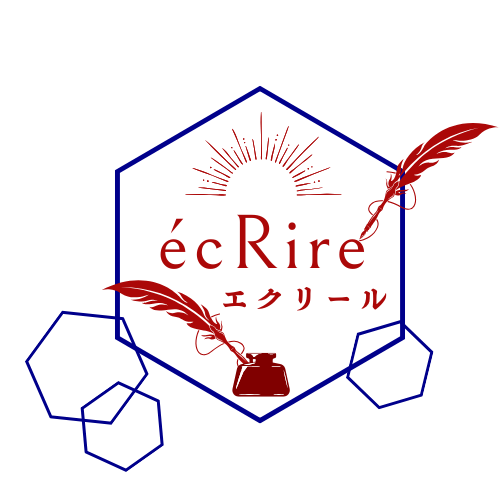最近、フランス人家庭の子育てについて考えることがあります。
きっかけは、こちらで連載している「わたしたちのこころの中」という往復書簡にて、ペレ信子さんが、子育ては、「子供のできないことを先回りしてやるのではでなく、子供が自分でできるようになる手助け」というお考えを述べてらしたことにあります。
わたしも、息子たちが自分で身の回りのことができるようになれば、と、子ども部屋にちょっとした工夫をしていたなぁ、と思い出したのです。
「遊び終わったら、ここに入れるのよ」と、大きなおもちゃ用の箱を用意したり、上着を掛けるフックも彼らの背丈の位置に付けたり、少し大きくなってからは、洗濯ものは自分のものを籠から取って、自分で畳んで、自分で棚に入れなさい、と躾けました。
その効果があった、とは、残念ながら言い難いのですが、少なくとも、「自分の身の回りのことは自分でするべきだ」という考えは多少なりともインプットされていると思います。
家政婦がいる暮らし
でもフランス人家庭では、こういう考え方は一般的ではないかも、とも思いました。というのも、フランスではミドルクラスの家庭であっても、そして専業主婦の家庭であっても、家政婦さん femme de ménage を雇っていることが多いのです。
ゆえに、身の回りのことも、必ずしも自分がしなくてはいけないことではなく、ましてや子どもに仕込むことでもなく。ま、「おもちゃは自分で片付けなさい」程度の躾はあるでしょうが、例えば、洗濯ものを子どもに「自分で畳みなさい!」という躾はないと思います。家政婦さんがきれいにアイロンかけて(下着にすら!)各人の部屋の引き出しに仕舞ってくれるからです。
うちも、義理の家族の田舎の家に滞在するときは、子ども達の役目は通いの家政婦さんが来ないときにテーブルセッティングを手伝う、といった程度です。あとベッドメイキングは各自するかな。掃除掛けとか、お風呂掃除、トイレ掃除はしないですし、することを求められてもいないですね。
フランスのママンVS日本の母親
日仏の子育てで「最も違う点」は、と聞かれれば、母親と子どもの関係性の違いだと思います。
こんなことがありました。息子が幼かった頃のことです。食卓にて、「もっと欲しい」とせがまれました。わたしも、息子にはもっと食べて欲しいという気持ちもあったので、わたしのお皿に残っていたステーキか何かを「はいはい、どうぞ」と上げたのです。すると義母から、「おやめなさい」というお声が。いわく、「それは貴女の分でしょう? 子どもがまだお腹が空いている? 我慢させなさい」ときっぱり。日仏違うなぁ、と思った瞬間でした。
わたしとしては、「一つしかないお握りを子どもの譲るのが母の愛(教科書にそんな話がありましたよね?)」、という気持ちがあります。自分のご飯を子どもに上げたためにわたしが空腹になったとしても我慢する覚悟を持っている、それが母親だと思っている。ところが、義母は子どもが「我慢すべきだ」というのです。フランスでは我慢するのは子どもなの? と驚きました。
ヨーロッパでは、18世紀にルソーが「子どもを発見」するまで、子どもは小さな大人と考えられていたそうですが、その名残を見たように感じましたっけ。
でもまあ、人の分も食べるというのは、確かにお行儀悪いことだし、少しくらいの我慢もいい経験かな、と納得もしたエピソードです。
まだまだあります
・道行く幼子ちゃん、ママンの両手が塞がっているのでスカートを掴んだら、「やめて!そんな汚い手で触らないで」とヒステリックに叱られていました。「子どもなんだから、しょうがないじゃない」という発想がないことに、またもやルソー(正確には、ルソー以前の、「子どもは小さな大人」という認識)が頭を過りましたっけ。大体、パンオショコラなんてものを包みもせずに渡して歩かせること自体どうよ、とか、手を繋いであげようよ、とか、スカートなんて洗えばいいじゃない? と思うことはたくさんありましたね。
・「息子が反抗期でうんざり。なので学校の寮に入れたわ」というママンには驚きましたっけ。え、それでいいの? 反抗期でも母親はぐっと耐えて見守らなくてはならないと思っていたけれど。当のママンは晴れ晴れとした表情でしたよ。
・鬱病になった娘を地方大学に送ろうとしたママンもいました。「だって、もう私、無理。彼女のムード・スイングにぐったりよ」と。その気持ちもわかるのですが、不安定な状態なのに、親元を離れ地方に送り込まれるお嬢さんも気の毒、というか不安じゃないの? 結局「カウンセラーに止められた」ため、自宅から通学できる学校に入れたそうです。
・他に好きな人が出来たので離婚する、というママン。思春期の子と受験生がいるけれど、「待てない」と。日本だったら、子どものためを思って、「思春期が過ぎるまで」「受験が終わるまで」しばらく仮面夫婦するんだろうな。
……色んなレベルで観られる日本とフランスの違いを、思いつくままに挙げてみました。批判というわけではないのです。ただただ「違うなぁ」というそれだけ。どのママンも、本当に良心的で、いわゆる良い親なのですよ。でもわたしとは「違う」ところもあるという。
そうそう、ちょっと外れたところでは、自分の人生相談を高校生の子どもに聞いてもらっているというママンもいました。三度(みたび)ルソーがよぎります。「子どもは小さな大人」で「母親は大きな子ども」かいな。
日本の母親は損?
通して感じるのは、フランスのママンたちはママンになっても女性であり人間臭いけれど、日本の母親は母親という生物に変容してしまう(させられてしまう?)ということです。
子育ては何が正解かわからない。いや、そもそも正解がないもの。日本の母親も、フランスもママンも、子どもを大切に思っているという点では一緒です。敢えてダメ出しするのであれば、日本の母親は、フランス人の感覚でみると「やり過ぎ、甘い、心配症」ですし、フランス・ママンは「冷たい、自分都合が多く、気まぐれ、操作的」ように感じます。
わたしは親となった時、子ども達の黒子に徹するという契りを自分の中で結んだところがあります。縁の下でいい、子ども達が立派に育つのなら、と思いつつ母親業をやっているのですが、このフランスで、「ママンこそスポットライトを浴びる人」(ママンの誕生日大切、食卓ではママンが主役、ママンは華、ママンの料理最高でしょう? ママ~ン!)という認識の中にいると、時折、非常に損な約束をしてしまった、と感じることも。
今さら、しょうがないですね。というか、子育てはやっぱり子どもたちが主役。幸せになってほしいですね、世界中の子どもたちに。