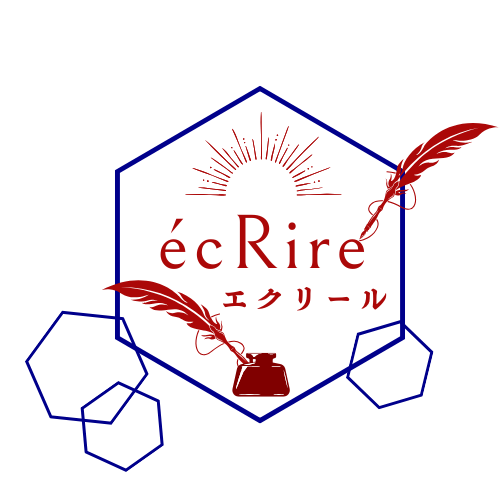3月21日、ベルサイユ
春真っ盛りを迎えたベルサイユよりボンジュール。家々の軒先からは溢れんばかりに、れんぎょうや桜が花開いています。日の出もぐんぐん早まっていて、理由なく浮き浮きするのですが、同時に、ついこの間まで凍てつくような冬だったのに、もう春? と、時の流れの早さにぞっとする思いもあります。
「フランスでは、最近の子供はスマホの影響で読書ができないそうですよ」と、信子さんの前回のお手紙にありましたが、そう言われると思い当たる節が。それは、若い人との会話です。話し始めて少しすると目が泳ぎ出すというか、戸惑っている印象を受けることがあります。あれは「大人と話すことへの照れ」かな、と考えていたけれど、もしかしたら、数十秒以上同じスクリーンを見ていられない「数十秒ルール」でわたしをスクロールしたくなっている、のかも。
ところで、スマホを使っているときは、脳の活動量が低いそうですね。スマホで得た情報はいつでも検索できるから記憶しなくてもよい、と脳が判断するらしいです。(『スマホはどこまで脳を壊すか』 (朝日新書) | 川島 隆太, 榊 浩平)
それで思い出すのは、フランスの小学校。宿題に詩や物語の暗記が多いですよね。ラ・フォンテーヌの寓話などは、子ども達の暗記に付き合ったお陰で知ったようなもの。
「ママ、明日までにこれをメモリゼ(暗記)しなくちゃいけないの」
と、息子がうんざり顔で暗唱するのを聴きながら、「こんな詰込み教育でいいの?」と訝しんでいたものです。でもある日、学校の先生をしているママ友より、「記憶力は脳の性質上、子ども時代に訓練するべきものだからなの」と説明されて、「へぇ、フランス、ちゃんと考えているんだね」と、感心したんですよね。
それなのに、そのあとスマホを与えたら(わたしが周囲ではスマホは早くて「中学から」という家庭が多いので)スマホ脳になってしまって記憶力・思考力が低下しちゃったって? なんたるアイロニー。
脳の成長のために、ゲーム中毒や有害なウエブコンテンツから子ども達を守るために、各国政府に子ども達のスマホ対策、してほしい!……けれど、開けてしまったパンドラの箱、スマホなしに戻すのは難しそう。
さて、信子さんの前回のお手紙には、「とめどなく思いを巡らせて」とありましたが、その一つ一つに「わかる!」と頷いておりましたよ。特に、「やりたいこと」と「やらなければならないこと」のバランス、という一文には、まさに! です。
やりたいことって、実は中々見つからない。わたしの場合はそうでした。これかな? と思って手を付けるけれど、飽きちゃったり、向いていなくてイヤになってしまったり。やっと見つかったのは、40代という遅さです。だけど、そこからも道は長く、そう簡単にものにはならない。それでもやりたい、という気持ちが、今はある、だけど……。
そうなのです、「やらなくてはならないこと」が幾つもあって。
わたしは、経済的自立と精神的自立は別物で、後者の方が大切だと思っています。でも前者ももちろん大切。わたしの「やらなくてはならないこと」は、経済活動と社会貢献活動でして、大切というより責務と考えている。そういった活動が幾つもあるので、そうなるとやりたいことに時間が割けないというジレンマが。
でもねでもね。「やらなくてはならないことがある」っていうのも幸運だな、と思うのです。役割がある、って有難いこと。やらなくちゃいけないけれど何をやったらいいのかわからない、と燻った時代が幾度かありました。あの焦燥感。好きではなかったな。
……まとまりがなくなっていますが、すみません、オチもありません。やりたいこととやらなくてはいけないことのバランス取るの、「ほんとに難しいですよね」、というそれだけ。
人生は、自分の意思で動かせる部分なんて、10%もないような気がします。残りは、タイミングとか運命というか、予想外な展開ばかり。思いがけない波が来たら、よけずに乗ってみる。来ないのであれば、じっと待つ。波に乗っているときも、待っている間も、自分の意思を忘れずに、大切に尊重して、努力して、きっといつかはあそこへ行ける、と信じて泳ぎ続ける。報われないかもしれないのに、全然違う場所に連れて行かれるかもしれないのに、ほんとけなげ。
そんな毎日だけど、大切で。
……ほんとにまとまりがない手紙。この辺で止めておきましょう。
まずは4月からのオンラインサロン「ÉOSエオス」です。続々とお申込みいただいています。感謝の気持ちで一杯です。ご期待に応えられるものにしたい、いや、しなくては。
信子さんもご参加くださるのですね、オンラインでお目にかかれるなんて、嬉しいです。
そちらも、そろそろ桜前線到来でしょうか。ご報告を楽しみにしています。
かしこ
美紀