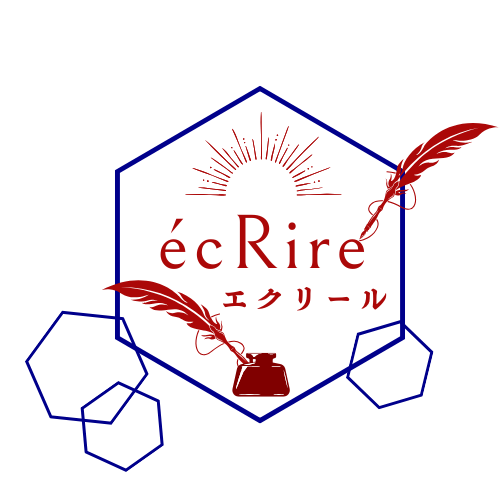4月25日 東京
桜の木がすっかり緑の葉で覆われて、足元のつつじの花のフューシャピンクが美しい東京です。さっぱりとした晴れの日と、しっとりした雨の日があって着実に夏に向かっているなと感じます。
八重桜よりもソメイヨシノを植えたい、その美紀さんのお気持ちよ〜くわかります。せっかく桜を植えるならソメイヨシノ派です、私も。この前、ラジオを聴いていたら、1年に二度咲きしたり、開花期間が1ヶ月もある品種改良された桜が出てきたと言っていました。それでもやっぱり咲き始めから満開へ、そして圧倒的な美しさのあとハラハラと散っていく、その栄枯盛衰を数日で見ることができるのが桜の良さかなと。人生の春夏秋冬の一瞬一瞬を大切に、という教訓のような気がしています。「日本文化は祈りを感じるから好き」という言葉を書いてくださいましたが、季節から人生を哲学できる日本人の繊細な感性が好きです。
「日本語に言霊を感じる」ということについて。日本語は、漢字とひらがなとカタカナを駆使していることで内容以上のヴィジュアルイメージからの表現ができる言語ですよね。私たちが日本語を読むときに、もちろん一語一語読んでいるのだけれど、実は漢字やカタカナなどの文字自体のイメージで写真を撮るように脳に意味を伝えている気がします。
私はフランス語で長い文章を読むとき、いつも最初は苦痛で仕方ないのです。26文字しかないアルファベットの限りない組み合わせでできた言葉をまるで暗号を解読するように読んでいく作業だからです。日本語は本のページを眺めたときに、漢字やカタカナなどのイメージがパッと目に入ってきて「あ、これは面白いこと書いてありそう」と読むモチベーションが上がります。ところがアルファベット26文字で書かれた本はパッと見ると「うわ、字がちっちゃい」くらいしかアイキャッチのポイントがないのです。欧文ネイティブの人はそうじゃないのかも。きっと文字の配列が意味のある言葉となってパッと目に飛び込むのかもしれませんね。
でもフランス語の面白いところは(他の欧文も同じでしょう)、最初は我慢して読んでいるうちに、話に引き込まれるとともに26文字の解読速度が上がってきて、ぐんぐん読めるようになるのです。感覚的イメージの日本語。論理的解読のフランス語。言語を文字から考えるのも面白いですね。
フランスの春は学生にとってテストの多い季節。息子さんたちの大切な時期ですね。希望の学校に合格されることをお祈りしています。私の方は、夫との二人生活に一時休符です。末っ子が学校の課題でインターンをする必要があり、日本に帰ってきています。フランスの大学は在学中にインターン(と言っても日本の就活のインターンではなく、実際に希望の企業で数ヶ月働く。卒業後その企業に就職するパターンもあり)を課しているところが大多数ですよね。そのためパリでインターンを見つけるのは至難の業だとか。コネがものを言うのに、パリにコネのない息子は自力で日本でインターンを見つけて帰ってきました。そして相当日本に帰ってきたかったようです。なのでしばらくはお母さん業を楽しむことにします。
息子を囲んで私たち夫婦と私の両親で復活祭のディナーをしました。定番の仔羊のもも肉にパスカルアニョーのお菓子。たくさん料理を作って食べてもらうのって良いなあと思えるようになったのはそれが日常じゃなくなったからでしょうか。
私も美紀さんに返事を書く時、気づけばたくさん書いています。書くことが頭の整理になっています。いつもお付き合いいただき、ありがとうございます。
Bon week-end!
信子