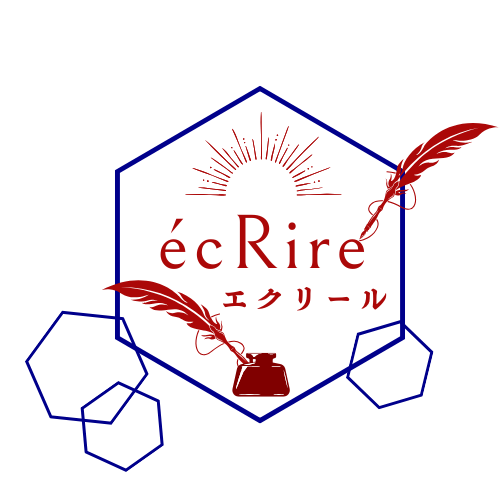8月22日、ベルサイユ
おはようございます。そちらはもうすぐ夕暮れ時でしょうからズレた挨拶でしょうが、お許しください。今、南の街、トゥルーズから寝台車に乗ってベルサイユまで戻って来たところでして、朝日が眩しく感じる中、お手紙を書いています。
今回の旅は、パリ→ボルドー→カルカッソンヌ→アルビ→トゥルーズ→パリを、電車で、正味4日で周りました。わたしも家族も初めての街ばかり。予備知識すらも持たずに出かけたのですが、満ち足りた旅でした。フランスは多様な国ですね。歴史的にも民族・宗教・文化が入り組んでいるんだなぁ、とつくづく感じました。
ボルドーは、「ミニ・パリ」と呼ばれているとか。確かに、青瓦の腰折れ屋根(マンサール屋根)のエレガントな建物は、パリのオスマニアン様式建築の高さを抑え目にした感じ。テラスやドアに美しいデザインの鋳鉄が多用されていて、ちょうど拙宅の木製のドアを変えようと考えている昨今でしたので、参考になりました。
カルカッソンヌは、中世の城塞都市。「カルカッソンヌを見ずして死ぬな」という文句で聴いたことがあっただけ、の街でした。ちなみに、このフレーズはフランスの「カルカッソンヌ」という悲歌の歌詞の一部とのこと。実に古い町で、ローマ時代に始まり、一時期はムスリム政権が鎮座し、スペインとフランスの国境が置かれた時代もあり、英仏百年戦争にも耐えたそう。蹄型の壁はローマ、どことなくアラベスクな窓はムスリム? テラコッタがスペイン風であって、チェスの駒、ルークのような形の塔にイギリスを感じ、でも全体はフランス、というそんな自分勝手な解釈をしました。
ちなみに、カルカッソンヌは、モンサンミシェルに次ぐ観光地なんですってね。
アルビという街はノーマークだったのですが、長男がどこかで見知り、提案したので立ち寄ることにしました。というのも、旅に関する長男の「ここってstylé(スティレ、格好いい)かもよ」というスポットは、当りが多いのです。果たして今回もそうでした。
キリスト教の異端とされる宗派によって造られた、アルビ大聖堂には圧倒されました。とにかく巨大で、大聖堂という言葉では足りなく感じられるほど。外観はレンガ造りで窓が少なく、収容所のような雰囲気。唯一、正門の彫刻が荘厳で素晴らしく、でも唐突感もあったり。それが中に入ると、パステルを多用したフレスコが壁・天井・柱、と全てに描かれていて、どこか日本の刺青を彷彿させられました。美醜を問われたら確実に「美」なのですが、異教的な何かを感じる……。不思議な大聖堂でした。
アルビは、この大聖堂のためだけ行く価値あり、なのですが、街自体も素晴らしかった! レンガの街並みが美しく、良質なレストランが何件もあって、タルン川は穏やかで清らかで、ピトレスク─ 絵にしたいような美しい景観がある街でした。
最後に立ち寄ったトゥルーズの街も素敵でした。若い人が賑やかに集っているエリアも楽し気で素敵でしたし、ガロンヌ川沿いの、エレガントでゆったりとした道も素敵。道がきれいで、「機能している街」という印象を受けました。(そういう意味では、ボルドーは意外と雑然としていたかも)
長々と、今回の旅の印象を書き連ねてしまいましたが、フランスの美意識の高さについて考えていた昨今だったので、答えの一部を見出だせたような気がして、それをお伝えしたくて。フランスの美しさは、川や丘陵などの自然、レンガなどの特産物(パステルもこの辺りの草から取れるそうです)、信仰、歴史から生まれているんだなぁ、とつくづく感じました。
その中に自分を浸して暮らしている人々、きちんと自分の街の、国の、歴史を理解し、自然を、文化を敬っている人々は、内側に美意識が出来てくるのではないかしら。今回の旅ではそんなことを思いながら、ひたすら見て、歩いて(男子家族なので、一日10キロは歩いたと思います!)の4日間だったのです。
前回の信子さんのお手紙には、信子さんの地元の「お気に入りの散歩ルート」を書いていらっしゃって、そこから漂ってくる東京の匂いにすっかりホームシックになってしまったわたしでした。異国フランスの文化が、東京らしく根付いている神楽坂界隈、素敵ですね。
思うに、わたし達は、自分の周りにある文化に、身を浸して、吸収しながら生きているのですよね。それを日々の暮らし─テーブル・コーディネートしたり、お料理したり、花を飾ったり、こうしてエッセイを書いたりしながら、outputしているんですよね。
間もなくこちらの往復書簡も一周年。9月からは、少し別のアングルで、わたしたちのoutputを紹介してみたいです。信子さんの「あのアイデア」、すごくいいと思いました。
アイデアの詳細に関しては、次回の信子さんのお手紙に委ねることにして、今日はここまで。これからシャワーを浴びて、洗濯洗濯!
残暑厳しいと聞いております。引き続き、ご自愛くださいね。
かしこ