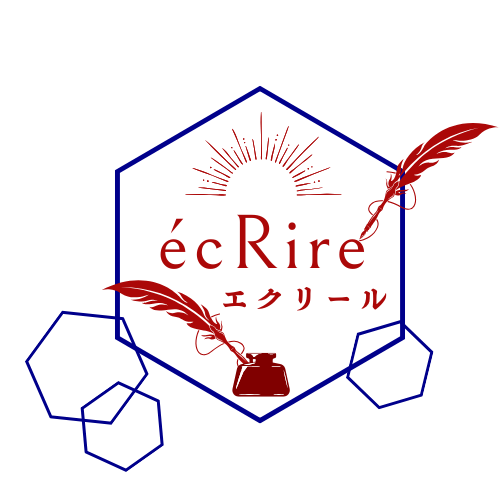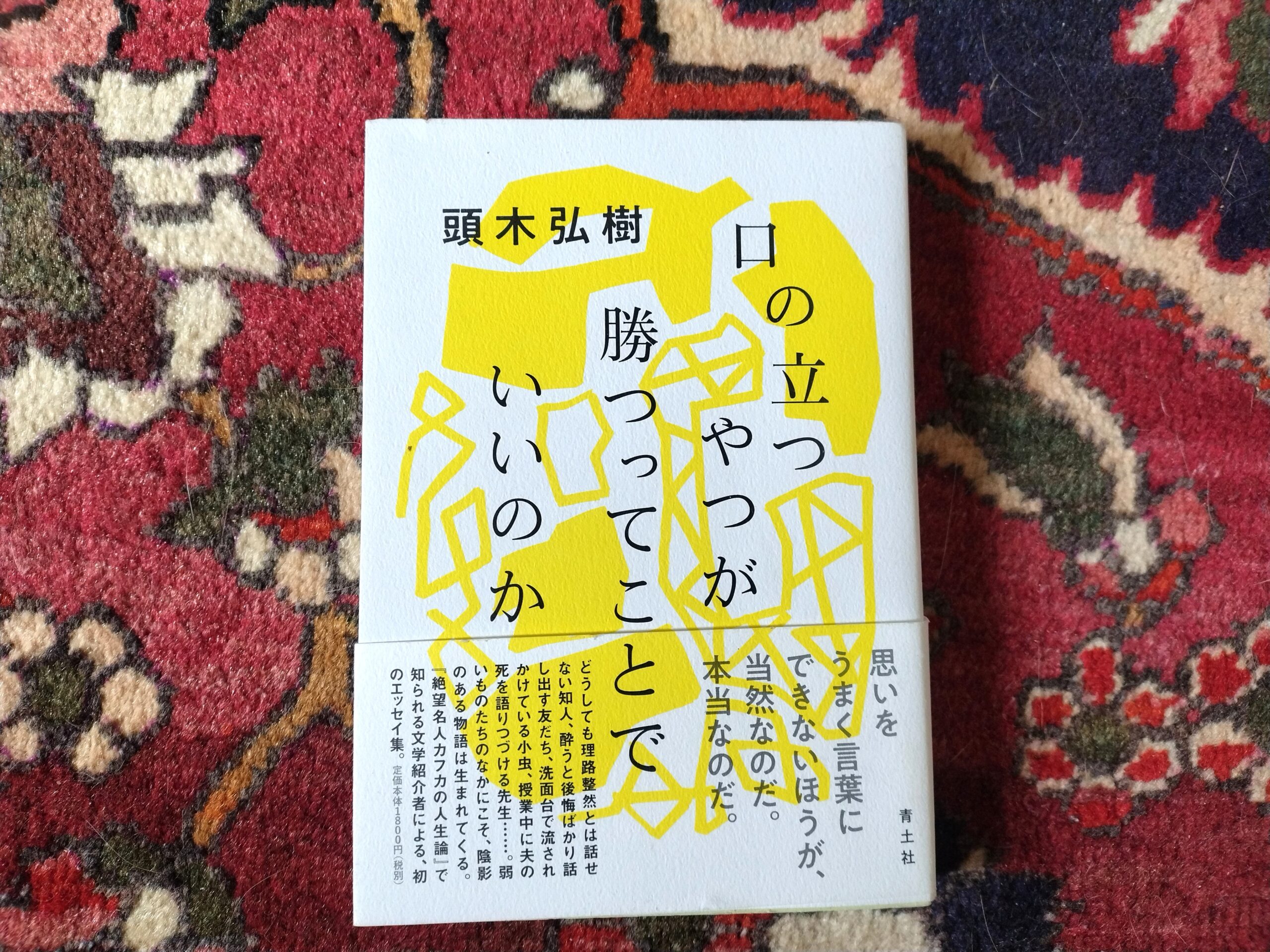みなさんは、どんな本が好きですか?
小説、エッセイ、ノンフィクション。小説であれば、その中にミステリーや恋愛ものなどがあり、エッセイの中にも、ライフスタイル、料理、旅行など、テーマによって色々あって。エッセイは日本語では随筆ですね。随筆といえば『徒然草』や『枕草子』はよく知られるところでしょう。
わたしは、実はエッセイはあまり好きではありません。エッセイだと、「いいこと言ってるなぁ」と感心しても、次のページを繰るころには、別の思い出やトピックに移り、せっかくの「いいこと」も記憶から流れて行ってしまって結局残らない。それで、頭の中では、エッセイよりストーリーがしっかり完結する(しないものもありますが)小説を上に置いていたのです。
でも、頭木弘樹さんのエッセイ『口が立つやつが勝つってことでいいのか』を読んで、「ごめん、エッセイ。勘違いしていたよ」と謝りたくなっています。
「エッセイ」という外来語は、フランスのミシェル・モンテーニュの随筆集『Essais』から来ています。16世紀終わりに出版されたものです。ウィキペディアには、『Essais』の中で、モンテーニュはこの本の目的は、人間、特に彼自身を、完全に率直に記述することであると述べている、とあります。読んでみたくなりますね。ちなみに、Essaisとは、試み、という意味です。
頭木弘樹さん、ワンサゲイン!
近年の書き手の中で注目を集めている頭木弘樹さん。こちら「本を読もう」のコーナーでも『カフカはなぜ自殺しなかったのか』を最初に取り上げさせていただきました。その以前には、わたしのnote でも『絶望読書』について書いています。
「自殺」(しなかったのか、ですが)や「絶望」という暗い熟語が続きますが、それが頭木さんの十八番。頭木さんは、絶望シリーズで知られる文筆家でらして、絶望図書館、絶望名言、絶望名人といった書籍だけでなく、絶望ラジオという長寿番組も持っていらっしゃいます。
頭木さんは、若い時に突然難病に侵され、13年も病院で過ごされたそう。難病なので完治することもない、未来もわからない。そんな絶望的な状況の中で、文学や落語に出逢い、後に文学紹介者となられ、昨今はエッセイも手掛けられている方なのです。
頭木さん、病気になる前は、読書があまり好きではなかったそう。なので、「大学で研究を重ねて」とか、「親が文豪だった」とか、「芥川賞受賞!」とかではなくて、「遅咲き」の、「独学」の、「在野」の、「文学を紹介する人」でらっしゃる。そこにも、わたしは目が行ってしまうんですよね。
というのも、わたしが数名の同志たちとスタートした、エオスというオンラインサロンと共通するなぁ、と図々しくも親近感を持ってしまうのです。
例えば、遅咲きという点においては、年齢的にもわたし達と頭木さんは多分同年代ですし、社会に出てからもそれぞれが独自に勉強し経験を積んできて、今もアカデミックな団体に所属せずに、フランスのアールドヴィーヴルに関する知識を紹介しています。ほら、共通項あるでしょ?
でも、頭木さんに戻りましょう。
頭木さんの文章の、難しい言葉を使わず、逆に尖った言葉も使わず、比喩こそあれ、わかる人にだけわかるような暗喩もなく、とことんわかりやすいところや、どこか控えめなところは、頭木さんのようなバックグラウンドを持つ方ならではの、親しみや謙虚さを感じます。
(エオスも、そうありたい、と心がけています)
だからといって、一流畑の書き手に劣るかと言えば、全くそういうことはなく、カフカに関しては今や右に出る人はいないのではないか、という勢いですし、『ミステリー・カット版 カラマーゾフの兄弟』はカラマーゾフという複雑で長い小説への理解が一気に深まる優れた解説書で、本編とペアで読むべき、と推したいほどに素晴らしくて。
(ごめんなさい、今、頭がエオスで一杯なので、ついつい口に出でしまうのですが、エオスの講義もほんとに素晴らしいんですよ。でも今度こそ、本の感想文に徹します!)
いよいよ本題に入りましょう。
今回の『口が立つやつが勝つってことでいいのか』は、途中から「すごい、いや、ほんとすごい」とため息とともに言葉を漏らしてしまったほど、エッセイというものの本領を見せつけられた思いです。
エッセイの醍醐味は余白にあり
エッセイの内容は、タイトルの「口が立つこと」がよしとされる風潮についての考察だけでなく、言葉に関する興味深いエピソードが幾つか続きます。そして後半は、エッセイらしく徒然なるままに話が繰り広げられていく、という構成になっています。
特徴として、まず一話一話が短く、飾らない語彙を用い、シンプルな文章で書かれているので読み易く。行間からは、「わたしは背伸びはしないんです、こんな感じでいいですか」と頭木さんから問いかけられているように感じられ、「うん、わたしもそれでいいです」とこころの中で親指Upします。
そう、問いかけられるんです。気づくと、頭の中で「わたしはどう思う?」「ねえ、それでいいの?」と、自分に問いかけていて。そもそもタイトルも、「勝つってことでいいのか」と問われていますし、それ以外でも、「後悔はしないほうがいいのか」「大好きな先生はいましたか?」「現実がすべてですか?」と問いかけスタイルの見出しが続きます。
あ、でも問いかけスタイルではあるですが、「考えなくちゃいけないのね」というプレッシャーはありません。文章のほとんどがご本人の思い出や考察が静かなユーモアを交えて書かれています。
そう、のしかかってくるような感じがないのも、頭木さんの素敵なところなのです。苦難バナシも多いのに、重苦しさはなくて。
頭木さんの短い文章からは、「今までたくさんのことを考えたし、そりゃね、思うことも一杯あるよ。けれど、それを全部吐き出すために書いているんではないんだ。ただね、なかったことにはしたくなくてね、だから手短に語らせてもらうよ」という声が聞こえてくるんですよね。で、淡々と文章が始まり、すっと終わる。もう少し書けただろうに、ぽとっとペンを置いた、そんな感じで終わるのです。そこには余白だけが残っていて。
その余白がいいんですよ。わたしが入る隙間というか、わたしが本の中に入れる居場所があるというか。一つのエピソードを読み終える度に、ページを開いたまま、「ふーん」と唸りつつ、しばし考え込む……。いや、「考え込む」というのは大きすぎるか。どちらかといえば「感じる」かな。本の中に入って、今、響いている何かを感じる。そして自分の思い出を掘り起こしたり、時にはあまり関係があるとは思えないような出来事について考え始めたり。で、お茶をひと口啜って、また続ける。
本の中で頭木さんは、親切心の大切さについて書かかれています。心身弱っているときは、愛など大きなものは望まないけれど、せめて親切心が欲しい、と。頭木さんの文章の余白には、「よかったらどうぞ、あまりお構いはできませんが」と部屋に入れてくれる、そんな親切心。優しさとはまた違う、「親切心」を感じるのです。
これぞエッセイ!
ここで気づくことが。
『口が立つ……』は、文体、そして書かれている内容とご自身が全て一致しているのですね、これってまさにモンテーニュがエッセイで試みた「人間、特に彼自身を、完全に率直に記述することであると述べている」ということではないですか。
頭木さん、素晴らしいです。独自のスタイルが確立されているんだなぁ。本当に素晴らしいなぁ。
とっても読み易くて、トリプルに素晴らしいエッセイ。
書いてくださったことに感謝。出会えたことに感謝。
次の作品が楽しみです。
いつか小説を書いていただけたら、と勝手な妄想をしています。